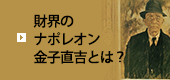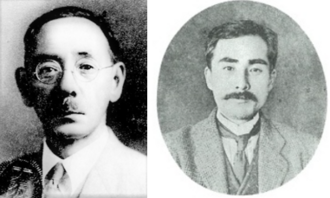帝国興信所が作成した「鈴木商店調査書」シリーズ㉑「東工業株式会社」(調査書P109~115)をご紹介します。
2025.9.20.
「鈴木商店調査書」をご紹介するシリーズの21回目です。
東工業の前身である東レザーは鈴木商店の化学工業部門への進出の門戸と言われています。明治40(1907)年、東レザーは当時レザー(模造皮革)部門としてはわが国最大級の工場として大阪府西成区稗島村に設立されました。
 同年、東京帝国大学の学生のまま太陽レザーで働いていた久村清太の発明による「艶消レザー」を製造するため、鈴木商店(資金を出資)、太陽レザー(工場を現物出資)、久村清太(レザー艶消しの特許を出資)の三者出資により東京レザー合資が設立され、久村はレザー製造に使用するビスコース(木材パルプを主原料とする再生繊維)の研究に着手しました。
同年、東京帝国大学の学生のまま太陽レザーで働いていた久村清太の発明による「艶消レザー」を製造するため、鈴木商店(資金を出資)、太陽レザー(工場を現物出資)、久村清太(レザー艶消しの特許を出資)の三者出資により東京レザー合資が設立され、久村はレザー製造に使用するビスコース(木材パルプを主原料とする再生繊維)の研究に着手しました。
明治41(1908)年、東レザーは東京レザー合資を吸収合併し、久村は東レザーの技師長となり、ビスコースの研究を続けました。 (左の写真は、東レザーの久村の研究室です)
金子直吉の強力な支援の下で続けられた久村清太(後・帝国人造絹糸社長)と大学の同窓であった秦逸三(後・帝国人造絹糸常務取締役、第二帝国人絹社長)の二人によるビスコースの研究は、苦難に次ぐ苦難の連続でしたが大正4(1915)年、「東レザー分工場米沢人造絹糸製造所」(後・帝国人造絹糸、現・帝人)での人造絹糸(レーヨン)製造の事業化として結実します。なお、同年東レザーはレザー、ゴム、人造絹糸など製品の多様化に伴い東工業に改称しました。
また、東レザーは神戸市武庫郡西灘村の敏馬神社に隣接するゴム工場(東レザー敏馬分工場)で自転車タイヤ、チューブ、ホース、パッキンなどを製造していましたが、さらに同地でのゴム工場増設の際に新たにファイバー製造工場を建設し、ファイバー(硬化繊維板)事業に着手しました。
 大正2(1913)年、鈴木商店は東レザー敏馬分工場でのゴム製造の拡大とファイバー製造開始を機に「ゴム・ファイバー工場」を分離し、金子直吉から援助を受けた依岡省三により設立されたボルネオ島サラワク(現・マレーシア・サラワク州)の日沙商会が経営する「ゴム農園」と合併すべく日沙商会を買収しました。
大正2(1913)年、鈴木商店は東レザー敏馬分工場でのゴム製造の拡大とファイバー製造開始を機に「ゴム・ファイバー工場」を分離し、金子直吉から援助を受けた依岡省三により設立されたボルネオ島サラワク(現・マレーシア・サラワク州)の日沙商会が経営する「ゴム農園」と合併すべく日沙商会を買収しました。
これにより日沙商会はゴム栽培から製造までの一貫体制が整いました。(左の画像は、日沙商会の工場 [旧・東レザー敏馬分工場] です)
大正3年(1914)年5月、日本輪業合資会社(現・ニチリン)が鈴木商店傘下のゴム製品販売会社として設立されましたが大正13(1924)年3月、同社は日沙商会のゴム部門を吸収合併し、製造から販売までを一体運営する体制として再出発しました。
鈴木商店経営破綻後の昭和9(1934)年、日沙商会は三井系の帝国堅紙と合弁で東洋ファイバーを設立しました。平成24(2012)年、同社は北越紀州製紙の系列となり、平成26(2014)年に北越東洋ファイバーに改称し現在に至っています。
なお、調査書の「会社の沿革 現況」には、東工業の当時の業況について次のように記されています。
「依然として続く販売価格の競争と一般市況不振のため、絶へず苦しい状態にあったが、突発した第一次大戦の結果、強敵である欧州製品の輸入途絶、とりわけ安価なドイツの製品が次第に無くなるのに伴い、内地製産の主力となれる同社の製品は漸くその優れた性能を発揮する機運に出会い、特に一般市況低落の結果として皮革、織物等が減退するのに反し、安価なレザー製加工品は却って需要を増加する傾向を生じ、‥‥」
また、同社の人造絹糸の事業については次にように記されています。
「同社の新事業とも言うべき人造絹糸は最初は幾多の困難に遭遇したが、次第に改良・進歩して、ほとんど輸入品に匹敵する優良品を確実に製造できるようになったので、さらに設備を拡張してひたすら増産をはかりつつある。そして、この事業は将来完全に外国から人造絹糸の輸入をなくし、さらに進んで外国に輸出するようになるべき将来性のある事業である。」
シリーズ⑥「日沙商会サラワック農場」(調査書P40~41)、シリーズ⑮「日本輪業合資会社」(調査書P87~88)もあわせてご覧下さい。
帝国興信所が作成した「鈴木商店調査書」シリーズ㉒「紡績業」(調査書P115~116)「佐賀紡績株式会社」(調査書P117~123)をご紹介します。