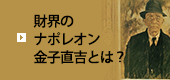帝国石油・旭石油(後に昭和シェル石油、現・出光興産)の歴史②
長崎英造による旭石油再建、長崎は昭和石油初代社長に
長崎英造が旭石油の社長に就任した際、後に「損害保険業界の父」と称された東京海上火災保険の各務鎌吉が「君(長崎)が(会社再建を)本気でやるなら」と言って、140万円の債務を肩代わりしてもらったという。(長崎英造遺稿より) 因みに各務は、高畑誠一らの要請により日商設立時に個人として出資するなど、鈴木商店の後継会社に対して種々支援を行っている。
長崎英造は会社再建に当たり、営業品目として高級潤滑油を主力とする手堅い経営方針を貫いた。同社は、まず昭和4(1929)年に徳山製油所を南満州鉄道に売却する。昭和5(1930)年にはライジングサン社との間の不利な原油・重油輸入契約を解消。営業品目も競争の激しいガソリンを避け、主として機械油、特にグリースを主力とし、ガソリン以外の燃料油(重油等)も販売。そして小型の製油所、グリース工場11か所を日本各地に展開した。また昭和7(1932)年には秋田県院内油田の試掘に成功し、原油採掘事業にも参画。
このような再建努力が実を結び、昭和8(1933)年には見事に復配を果たす。昭和13(1938)年には彦島工場を拡充。昭和16(1941)年には当時の東部および西部のグリース工業組合所属業者を買収・統合して日本特殊グリース(現・日本グリース)を設立。さらに同年、南海石油を吸収合併するなど、配当復活以降の積極策が実り、後述の3社合併時には石油総合企業の雄として業界に確固たる地歩を築いていた。
昭和12(1937)年の日華事変勃発により戦時体制に突入した日本政府は、石油業法(昭和9年制定)の国家統制目的を遂行するため、至上命令として民間石油会社の整理統合を進めた。まず合併に動きだしたのは、早山石油(新潟県)と新津石油(新潟県)であった。両社は昭和16(1941)年に合併契約書に仮調印し、商工省燃料局長官・東栄二に提出したものの、東はこの合併に旭石油を加えるよう3社に指示を出した。これを受け3社は協議に入るが、旭石油社長の長崎英造は合併比率や資産査定において異議を唱えるなど、なかなか意見がまとまらず交渉は難航する。
しかし、紆余曲折を経ながらも最終的には昭和17(1942)年3月に合併調印に至り、旭石油は昭和17(1942)年8月1日をもって早山石油・新津石油と合併し、昭和石油が誕生する。初代社長には長崎英造が就任。(会長:早山石油・川崎汽船社長、鋳谷正輔、副社長:新津石油専務、小柳牧衛) ここにおいて昭和石油は、採掘、船舶、製油、販売を手掛ける日本石油に次ぐ総合石油会社となった。以後長崎は、3社合併による国策会社・昭和石油の難しい舵取りを担うことになる。
この時点で全国の石油精製会社は、次の8社に統合・再編成された。
①日本石油 ②昭和石油 ③丸善石油 ④大協石油 ⑤東亜燃料工業 ⑥三菱石油 ⑦興亜石油 ⑧日本鉱業
あえて、歴史と規模の両面からこの8社のランク付けをするならば、第1位にランクされるのは明治21(1888)に設立された日本石油(日石)である。当時、日石は採掘、船舶、製油、販売にまたがる超大型総合石油会社で、戦前、圧倒的に強力であった外油会社・ライジングサン、スタンダードの両社に対抗し得たのは日石のみであった。
第2位にランクし得るのは昭和石油であろう。大正11(1922)年に発足した新生・旭石油の規模は日本石油に大きく劣っていたとはいえ、日本石油と同様に採掘、船舶、製油、販売にまたがる総合石油会社であり、早山石油と新津石油を合体すると、総合的には昭和6(1931)年設立の三菱石油、昭和14(1939)年設立の東亜燃料工業の地位を凌駕していたと思われる。