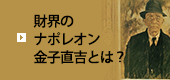日本セルロイド人造絹糸(現・ダイセル)設立の歴史③
第一次世界大戦の勃発がセルロイド業界に飛躍をもたらす
創立以後、経営難に陥り苦闘を続けていた日本セルロイド人造絹糸と堺セルロイドの両社は、大正時代に入ると、技術力の向上とともに徐々に危機的状況を脱していった。しかし、続いて両社の間で無理な生産競争が起こり共倒れの恐れさえ生じたため、危機感を抱いた両社は合併を協議することとなった。当時の生産実績は、網干が6万ポンド/月、堺が4万ポンド/月で合計10万ポンド/月であったが、市場の消化能力はこれを下回り生産過剰に陥るため両社で8万5千ポンド位に引き下げようとしたが、結局物別れとなってしまう。それ以来というもの、両社は相変わらず互いに苦闘の日々を送っていた。
このような状況下において、大正3(1914)年7月にヨーロッパにおいて第一次世界大戦が勃発した。このことが、わが国に未曾有の好景気をもたらし、セルロイド業界にも一大転機をもたらした。
たちまちにして、ロシアおよびルーマニアからわが国に対し大量の火薬製造が発注され、日本セルロイド人造絹糸網干工場にもロシアのゲルモニウス少佐が工場視察に訪れ、火薬製造契約が締結された。日本セルロイド人造絹糸としてはセルロイドへの未練は強かったが、時局の要請と経営難という窮状打開のため大正4(1915)年3月に火薬製造が開始された。この時経営陣は西宗成二支配人を除いて大半が入れ替わり、技師達も退職。一方、ロシアからは監督官が着任した。結局、特需とも言うべきロシアからの注文による火薬製造高は1,000トンを超え、相当の利益を上げることができ、同社の経営はようやく安定に向かった。
一方、ヨーロッパのセルロイド業界は各国がみな軍需品の製造に集中したことにより、セルロイドの製造には全く余力がなかった。このため、わが国にセルロイド生地および加工品の注文が殺到し、活況を呈し始めていた。大正6(1917)年7月、日本セルロイド人造絹糸はセルロイド製造に立ち戻り、その年の9月には東京化学工業博覧会から無煙火薬とセルロイド生地に対し名誉牌が授与されるほどになった。このころ、同社では独自にセルロイド事業を企図していた岩井勝次郎と西宗茂二がそれぞれ取締役、支配人を辞任し、専務に島村足穂、支配人に下村尚美が就任し、経営主体は鈴木商店に移行している。
一方、終始セルロイド製造に邁進していた堺セルロイドは、ヨーロッパからのセルロイドの大量注文に応ずべく製造に全力を傾注していった。同時に国内の加工業者からの注文も増加した。その結果、営業成績は向上し、販路も欧州市場の他、オーストラリア、インド、南洋等に拡大された。ここにおいて同社の事業の基礎と内外市場に飛躍する素地が確立したといっていいだろう。
このころ、第一次世界大戦に起因するセルロイド業界の活況を反映するように、セルロイド製造会社が相次いで設立された。大正5(1916)年、大阪では岩井商店の岩井勝次郎が西宗茂二を専務にし、元網干の技師を招いて毛糸、ソーダ、ベークライト等の製造をも含めた大阪繊維工業(後に大日本セルロイドに合流)を設立した。セルロイド製造の重要性を認識していた岩井は、日本セルロイド人造絹糸が火薬製造に特化するようになった大正4(1915)年頃、独自にセルロイド工場の建設を企図していたのである。大正6(1917)年には東京セルロイド(後に大日本セルロイドに合流)が設立された。
また、明治42(1909)年には、乙宗源次が三国セルロイド(後に大日本セルロイドに合流)を設立。その他、大阪においては東洋、十河、的場、西田、淀川、筒中、小山、国際、中谷、大正の諸工場、東京においては東亜、東洋、青木、永峰、千種、一城、秦、十全の諸工場のいずれも大正の初期に新設、増設をもってセルロイド生産・加工に生産高を競い、大戦の勃発とともに大いに躍進した。